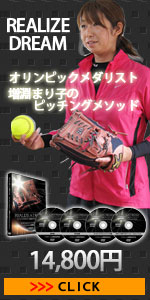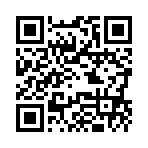2010年04月27日
授業料という考え
昨日ラジオを聞いていたら、こんな話がでてきました。
授業料の話【福沢諭吉】
上記こちらから転用
http://www.yomiuri.co.jp/education/kouza/nyushi/0911/n0911_1.htm
慶應義塾を創設した福沢諭吉【一万円札】が、
日本で始めて授業に対しての対価を求めた、という話ですね。
福沢諭吉が授業料を求めたとき、
反対する人がほとんどだったそうです。
今までお金を払わないで、学ぶことができたわけですから、
これまでどおりにしてもらえたら授業を受ける人からすると助かるわけですが、
その授業を行う先生の生活を考える、
授業をより充実させるために必要な経費というのも考えると
学校が発展しないとより良い学びが得られないということですね。
経済的自立ができていない機関での
授業がどれだけ充実したものになるか、
本当に指導を受ける人達のことを考えると、
サービスに対する対価は必要だと思います。
今でこそ、教育の対価は当たり前になっています。
そして、
スポーツ指導の対価も当たり前になる時代を作っていく必要があるのではないかと思い、
僕は日々活動しています。
子どもたちに良い指導を行うために
指導者は多くの時間と
多くのお金を使っています。
指導が継続して行えるように、
こどもたちが指導をずっと受けられるように、
ボランティアではとても厳しいと思います。
子どもたちにより良いスポーツ環境を提供するために、
必要なこと、一歩ずつ取り組んで行きます。
授業料の話【福沢諭吉】
授業料という制度を日本で初めて導入したのは福沢諭吉の慶應義塾だそうです。それは慶應4年(1868年)慶應義塾が芝新銭座(現在の港区浜松町1丁目)に新校舎を建設して本格的に学校経営を始めた頃です。『福翁自伝』によるとそれまでの私学は、入学時に「束脩(そくしゅう)」という入学金を払い、あとは盆暮にお金か品物に熨斗をつけて先生に差し上げていただけだったそうです。それを福沢諭吉は「教授も矢張り人間の仕事だ、人間が人間の仕事をして金を取るに何の不都合がある、構うことはないから公然価(あたい)をきめて取るが宜(よ)い」と考えて授業料という制度を導入しました。この合理主義精神は、札を検めるのに邪魔だから水引も熨斗もいらないという徹底したものでした。師の薫陶への感謝の念が、教育サービスの対価である授業料に変化した瞬間です。
上記こちらから転用
http://www.yomiuri.co.jp/education/kouza/nyushi/0911/n0911_1.htm
慶應義塾を創設した福沢諭吉【一万円札】が、
日本で始めて授業に対しての対価を求めた、という話ですね。
福沢諭吉が授業料を求めたとき、
反対する人がほとんどだったそうです。
今までお金を払わないで、学ぶことができたわけですから、
これまでどおりにしてもらえたら授業を受ける人からすると助かるわけですが、
その授業を行う先生の生活を考える、
授業をより充実させるために必要な経費というのも考えると
学校が発展しないとより良い学びが得られないということですね。
経済的自立ができていない機関での
授業がどれだけ充実したものになるか、
本当に指導を受ける人達のことを考えると、
サービスに対する対価は必要だと思います。
今でこそ、教育の対価は当たり前になっています。
そして、
スポーツ指導の対価も当たり前になる時代を作っていく必要があるのではないかと思い、
僕は日々活動しています。
子どもたちに良い指導を行うために
指導者は多くの時間と
多くのお金を使っています。
指導が継続して行えるように、
こどもたちが指導をずっと受けられるように、
ボランティアではとても厳しいと思います。
子どもたちにより良いスポーツ環境を提供するために、
必要なこと、一歩ずつ取り組んで行きます。
Posted by 沖縄SUN at 06:39
│雑談